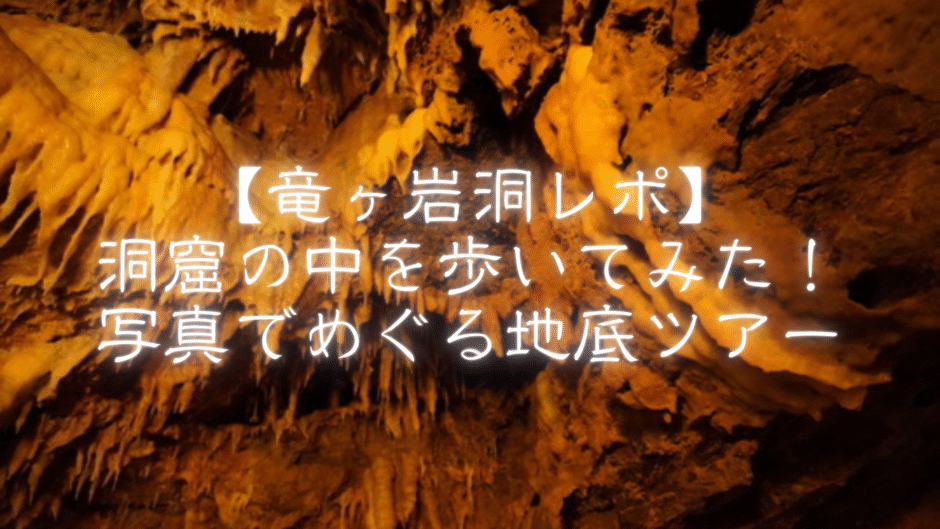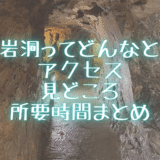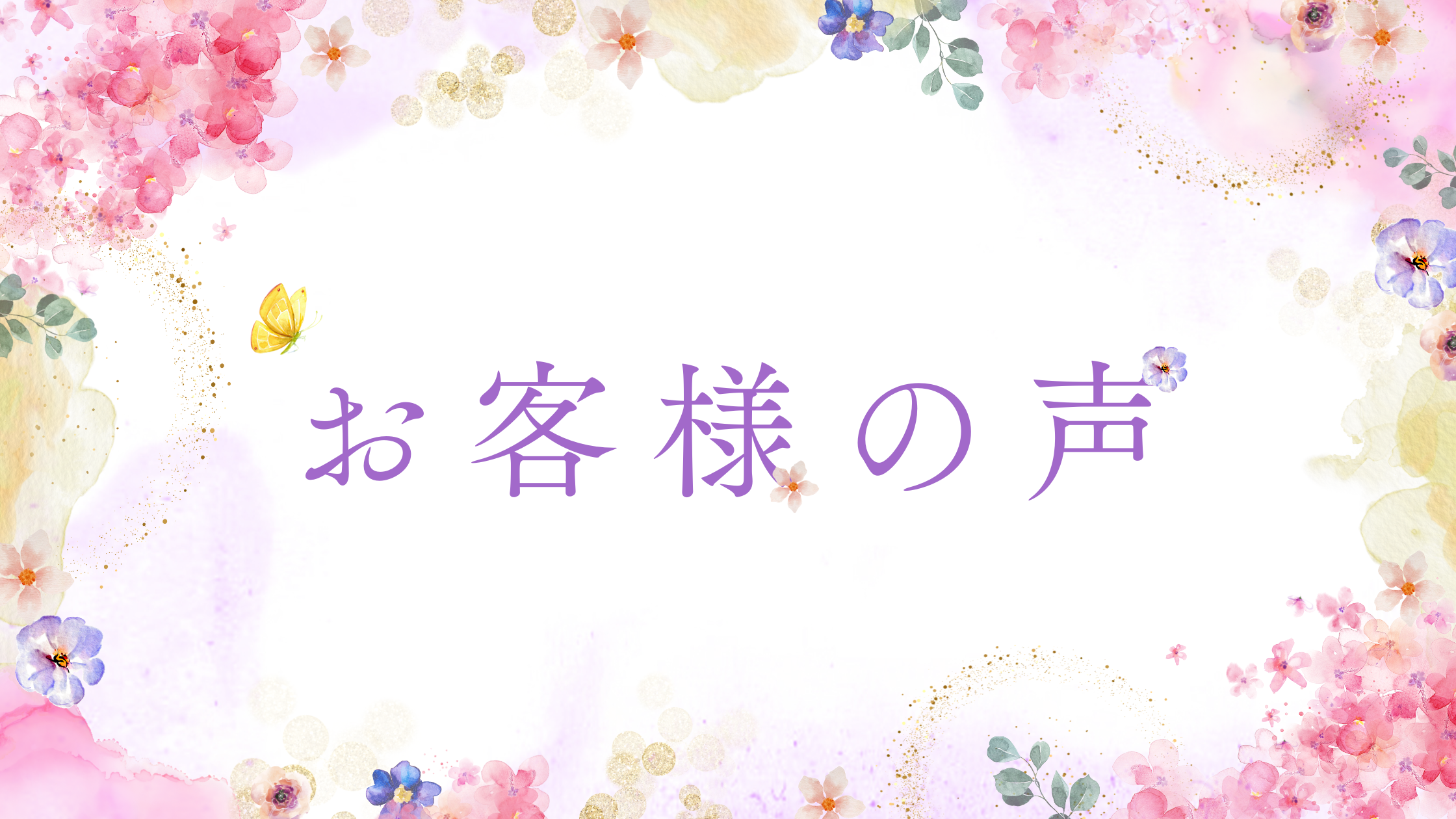この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
浜松市北区にある鍾乳洞「竜ヶ岩洞」へ行ってきました。
この記事では、細かい解説よりも、
「こんなところだよ〜」という雰囲気が伝わるように、
ほぼ写真でお送りします📷
あと、一眼レフ持ってったのですが、写真下手クソすぎてごめんなさい←
入口と最初のエリア



洞窟内の気温は18℃。
チケットもぎりのところにもデカデカと書かれていました。
中に入るとすぐにコウモリの展示と、コウモリの顔はめパネル。
「しつけてるから、人に慣れてます」と、入口の優しそうなおじさんがコウモリの説明しに来てくれます。
このコウモリの展示ゾーンも洞窟内のようです。
コウモリの展示ゾーンを抜けると、そこから本番スタート。

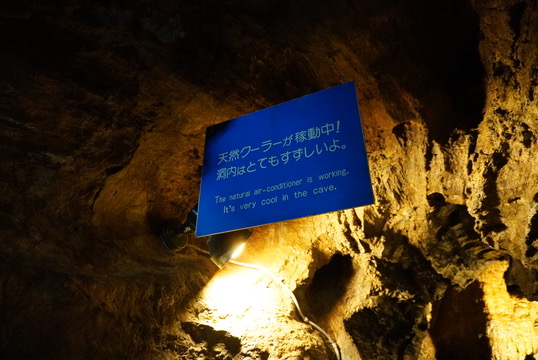



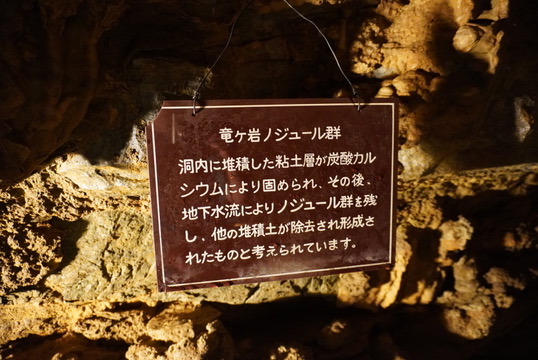










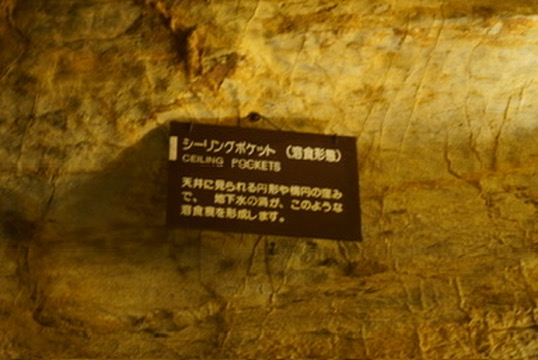






ところどころ広めの道があります。
ものすごく時間をかけて見てしまったので、後ろに人が来たら「お先どうぞ🙏」とちょいちょい譲っていました。
登竜門〜喜びの窓
途中、二手に分かれているところを発見。
「どっち行く?」
「俺は無理かも」
と、御夫婦がお話しているのを横目に見ながら、私は狭い方を通ってみることに。
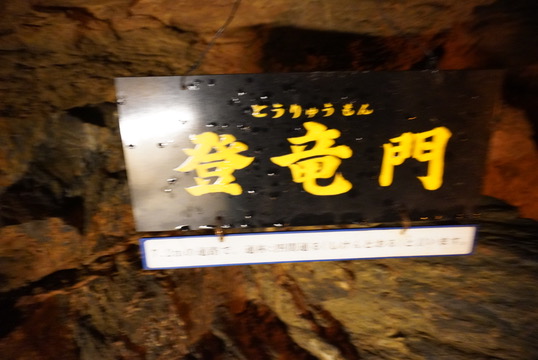

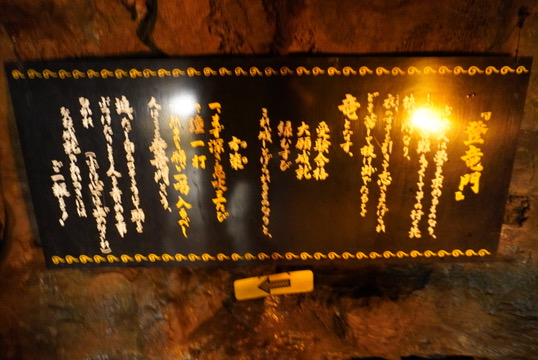
しかし、人がたくさんいたので、時間をかけられません。
ザクッと写真を撮って、鐘を叩かずに進むことに。

めちゃくちゃ狭いですし、高さも低いです。
私は身長156cmくらいなので行けましたが、成人男性は難しいかも。
見ての通り、めっちゃ幅が狭いので背を屈めて通るのもギリギリな感じです。
リュックが引っかかりそうでしたが、標準と肥満のハザマの私は何とか通過。
良かったー、痩せてて
登竜門を抜けると、コウモリの間です。
天井にぶら下がる野生のコウモリ発見。
このあたりを歩いていると、コウモリが横切ってくることもあるので軽くビビります。

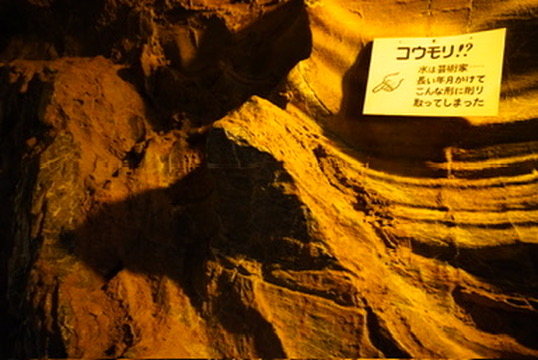

発掘当時「ここで鍾乳洞は終わりだろうか」と諦めかけていたとき、
タバコの煙で空気の流れに気づいたそうです。
空気の流れを信じて土を掘り進めていくと
奥にも鍾乳洞が続いていることを発見できた重要ポイントです。

今はその横を歩いて通れるので、
喜びの窓を通らなくても狭さやすごさを実感できます。
ううう、はさまりそうで怖いwww
この穴を通すのに難攻したため、当時「うらみの窓」という候補もあったですが「こんな嬉しいことはない」と”喜びの窓”と命名されたそうです。
かなり進んだように感じましたが、このへんでようやく一般公開されている部分の4分の1です。
中央エリア
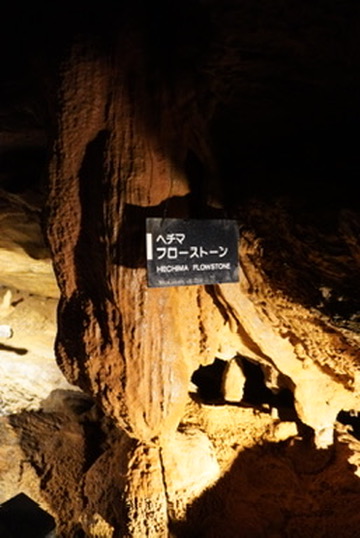
ヘチマ、マジでヘチマ。
フローストーンとは鍾乳石の形の種類の一つです。
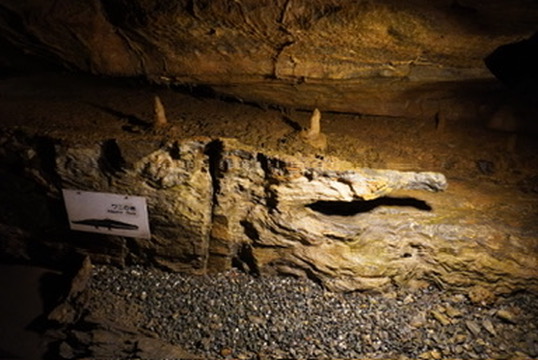
ワニだわに!!!!







めっちゃ狭く、さらに坂道になっています。
くっ!
ここは俺に任せて先へ行け!!!
ってやりたかったけど、後ろから人がいたので断念。


ここからはちょっとオ・ト・ナ 生命の神秘の時間(?!)
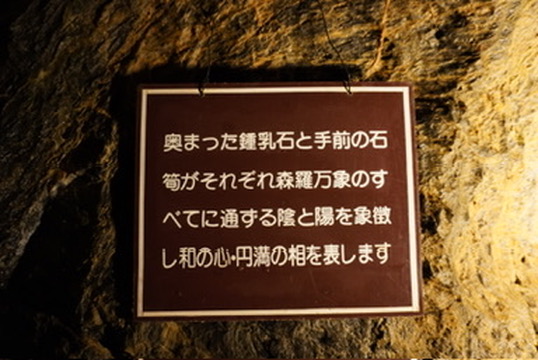
ほーう???
なるほど??

はじめはよくわからなかったのですが、心が汚れた大人なので言わんとしていることを理解できました。
これを自然が作ったってのすごいし、森羅万象・陰陽を象徴・・・
うん、なるほど。
子孫繁栄しそうだね✌
ここからは竜の抜け穴ゾーン。


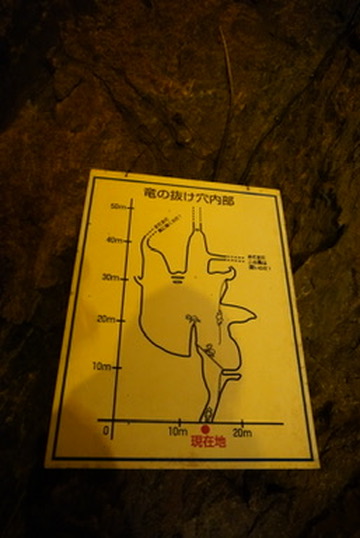
上を登っていくと、更に鍾乳洞が続いているそうです。


こんな感じで神々しい名前がつけられています。
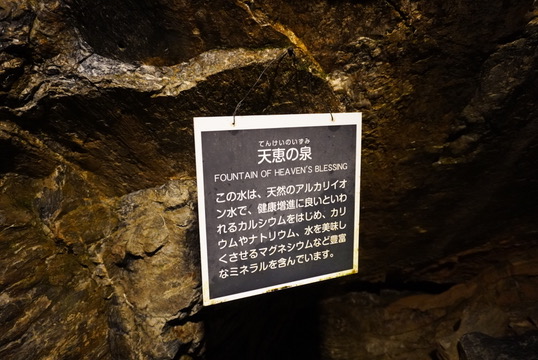
鍾乳洞の中には細い川が流れている場所や、泉になっている場所がところどころ現れます。


このあたりでようやく折り返し地点です。
黄金の大滝周辺
ザーーーーー!
っと水が落ちる音が響いてきます。
さて、ここからは撮影禁止スポット。
黄金の大滝エリアです。
滝が落ちる真横をビッショビショの階段を降りていきます。
このあたりが混むと危険なので、撮影は禁止されています。
あの”喜びの窓”を通って、この大滝を発見したときのことを思うと、胸が熱くなります。
「わーい、滝だー!」
とテンションが上がりましたが、よく考えるとここは地中。
土の中なのに、地上と同じような滝。
すごいな、やっぱり。


肉眼で見たときは「うおおおおお! マジで龍の腹っぽい!!」と思ったのですがw
写真むずかしいw
後半エリアは青い照明が増えています。
後半エリア
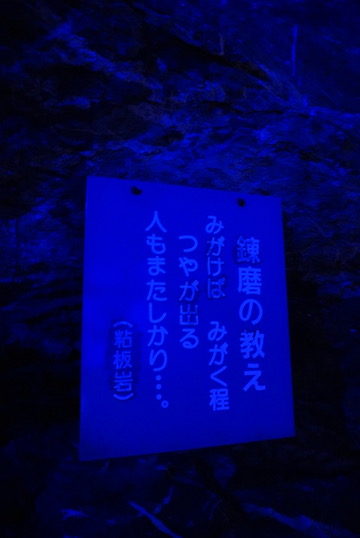




どういうこと?
と思ったのですが、よーく見ると宮司さんの後ろ姿のように見えます。
最終区間:出口まで
ここからラストスパートです。
竜ヶ岩洞メインの一つでもある鳳凰の間の前では、行列ができていました。
それもそのはず。

鳳凰の間は行き止まりになっているので、前の人が出てくるまで待つ必要があります。


翼を広げた鳳凰のように見えます。
この鳳凰の間にはあらゆる鍾乳石の形が集まっています。

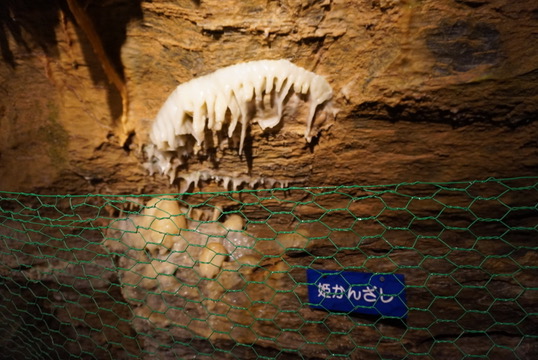
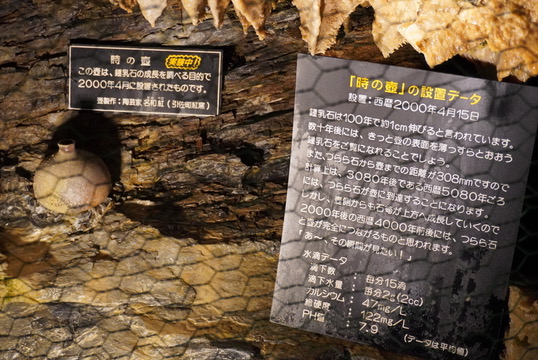
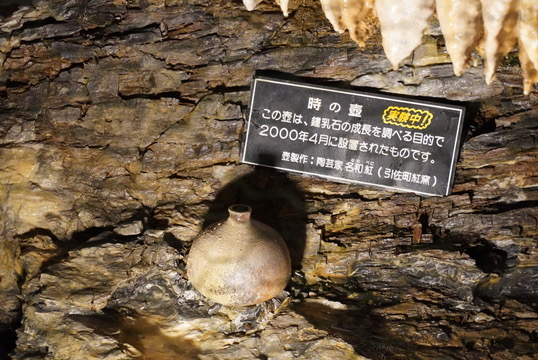
鍾乳石は1cm伸びるのに100年かかるといわれています。
鍾乳洞の中は今も地表から染み込んだ水が流れているので、
今も鍾乳石は成長し続けています。
この壺から鍾乳石が顔を出すのは何年後でしょうか。
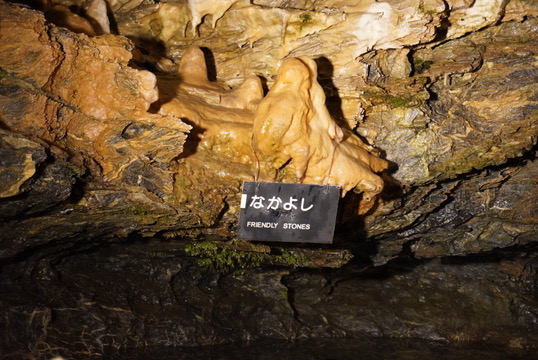
ちょっと見にくいですが、寄り添い合って座っている人型の鍾乳石が二体。
かわいい。


そろそろ洞窟も終わり。
出口には洞窟資料館があります。

資料館には竜ヶ岩洞の歴史や、鍾乳石や鍾乳洞について、また洞窟内の生き物についての展示がありました。
洞窟内の注意点
所要時間は通常だと30分、混雑時だと45分らしいです。
私みたいにじーっくり見ると1時間以上かかります。
洞窟内は手すりがあるのですが、結構滑りやすいのでスニーカーをおすすめします。
あとね、少しですが意外と濡れます。
なにせ現在進行形で地下水が洞窟内に垂れているのです。
そして足元から冷えます。
かなり冷えます。
酷暑シーズンのため、半袖で訪れましたが足首まで長さのあるジーパンで正解でした。
冷えやすい人やお腹が弱い人はウインドブレーカーも必須です。
年中通して18℃くらいなので、冬に行くと逆にあったかいらしいけどね。
ちなみに荷物はできるだけ身軽にしたほうが良かったなーと思いました。
私はトレッキング用のリュックで行ったのですが、登竜門とか狭いとことかでちょっと後悔w
カメラとスマホ、財布、上着などの最低限の装備だけが良いかもしれません。
さてさて、竜ヶ岩洞の内部レポはこのあたりで終了です。
今回ご紹介したのは、鍾乳洞内の一部です。
めっちゃ載せたけど、これでもほんの一部!
でも、やっぱり現地で肉眼で見てもらうほうが良いので、ぜひぜひ足を運んでみてくださいね!
ちなみに竜ヶ岩洞へのアクセスなどについては
こちら↓の記事で詳しくご紹介しています。